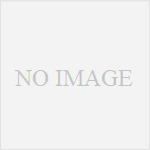「茄子の煮びたし」
「あなた、茄子はお好きでしたよね」
そう言いながら、まな板の上に紫の茄子を並べた。雨の午後、彼がふいにやってきた。傘を持たず、ワイシャツの肩が濡れている。ドアの隙間から、湿った夏の終わりの匂いが部屋に入り込んだ。
「ごめん、近くまで来たもんだから」
口実にもならない言い訳。だけど私たちは、もうずっと前から、言葉の帳尻を合わせるのをやめていた。
彼とは、会社の資料室で偶然、袖が触れたのが最初だった。小さな紙やすりのような、その感触が妙に頭から離れなかった。二度目は、会議の帰り、地下鉄の駅までの道。手が、また、ほんの少し触れた。
「偶然って重なるんですね」
そう言った私に、彼は笑わずに言った。「偶然じゃないかもしれない」
それからだった。二人で駅のそばの喫茶店に入るようになり、互いの好みや嫌いな季節の話をするようになった。私が一人暮らしだと知ったときの、彼の視線を今も覚えている。深くはないけれど、底の見えない池のような目だった。
鍋に油を熱し、茄子を素揚げする。じゅっという音が、二人の間の沈黙を少しだけ軽くする。
彼はソファに座り、何も言わずに私の背中を見ている。視線が肌に触れるような錯覚。私はあえてそれを無視して、煮びたしのだしを準備した。
「まだ早いですね。冷まして、味を染み込ませないと」
「急いでないよ」
その言葉が、喉の奥で震えた。急がなくていいと言われたことが、どうしてこんなにも嬉しいのだろう。
夜になると、雨音が少し強くなった。蝉の声も、もう聞こえない。彼は焼酎をちびちび飲み、私は冷やした煮びたしをそっと皿に盛る。
「ほんと、うまいな……」
彼が言った瞬間、私はようやく椅子に腰を下ろした。けれど、箸には手をつけず、ただ、彼の顔を見ていた。
「……ずるいですね」
ぽつんと、こぼれた言葉に自分で驚いた。彼も驚いたように顔を上げた。
「なにが?」
「こうやって、なんとなく来て、なんとなく居て……わたしだけ、待ってるみたいじゃないですか」
そのとき、彼の目がゆっくり動いた。皿から、私の指先へ。指先から、腕、肩、鎖骨へと。
「……待たせたのは、俺のほうかもしれない」
彼は立ち上がると、私の手を取った。いつもの不器用な動作で、けれど確かな力で。私は身をまかせた。抵抗する理由も、意味も、もうとうにどこかに置き忘れていた。
シャツのボタンをはずす音が、雨音に混じる。襟元に触れた指先は熱く、頬に落ちたひとしずくの雨がひやりとした。彼の唇が、肩に、そして胸元に触れたとき、私はほんの少しだけ目を閉じた。
音を立てぬよう、カーテンが揺れる。夏の名残の風が、肌をくすぐる。
長い時間をかけて近づいた距離を、たった数分で縮めていくような、そんな感覚。言葉は、もはや意味をなさない。ただ指先が、唇が、背中が、互いを確かめ合う。
彼の背中に腕をまわすと、その身体が少しだけ震えた。男の硬さと、寂しさがまじった匂いが胸の奥に沁みてくる。
すべてが終わったあと、彼は何も言わずに私の髪を撫でた。
朝方、目が覚めると、彼はいなかった。まるで、最初から居なかったかのように。
キッチンに、空の皿と、ペンで書かれたメモ。「今度は俺が、煮る番だな」
笑っていいのか、泣いていいのか。私は鍋に残った茄子を、そっとひとつ口に運んだ。味はもう、変わっていた。