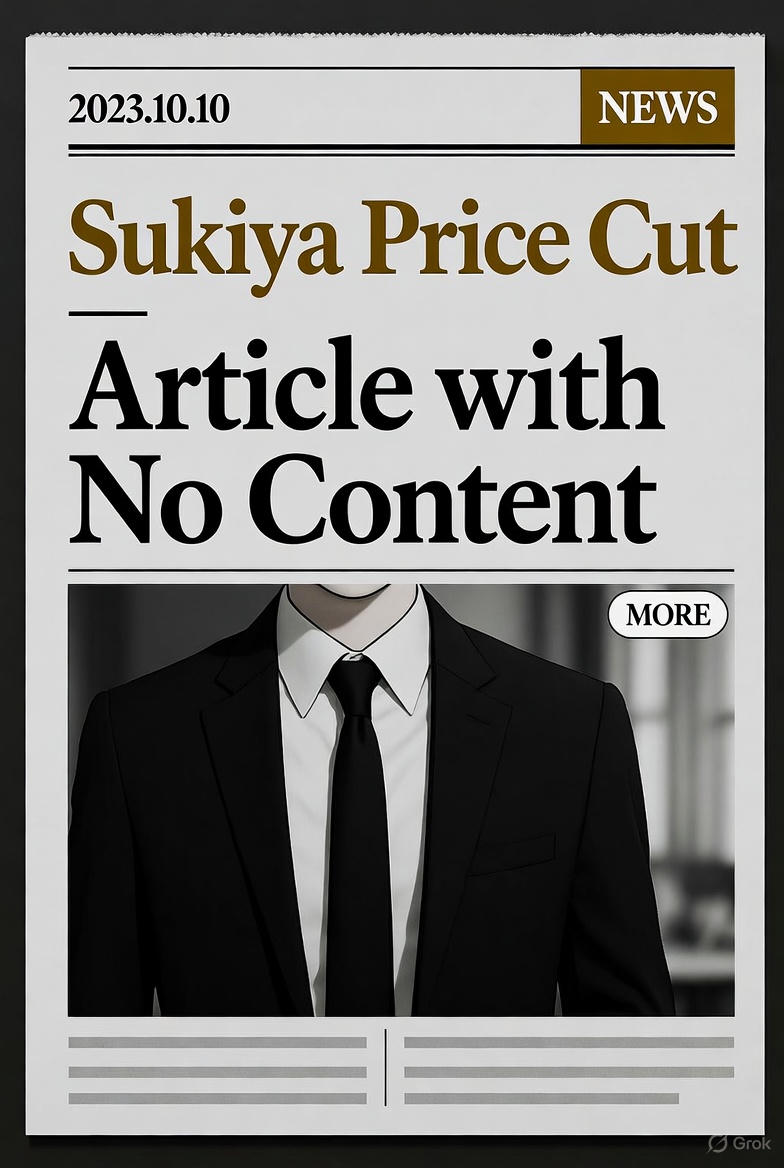
昼刻コラム「なぜすき家は値下げするのか」

昨今の物価の値上がりは胡散臭く感じるね。そりゃ値上げできるものなら売る方は値上げしたほうがいいわけだから値上げするよね。なんか僕はそれに付き合いたくなくて、とことん食べる量を減らそうと思ったよ。そしたら6キロ痩せちゃった。値上げで痩せたってそこだけきくと危険な感じがするね。
物価が上がっているのは日本だけではないみたいで、そこからすればまだ、そこまで高くはないともとれるという人もいる。そうかもしれない。
経済なんてのは自分で変えられないものなので、どう付き合うか、か、付き合わないか、ですね。
これは田中式ダイエットとでもいいましょうか。
それでもこの話をしたら、好きな食べ物食べなきゃ生きている意味がないって言われました。
夕刻コラム「どういうぶつかり方?」

こういう、内容の見えない記事は嫌いではない。
とりあえずアップしなければいけない状況になっている人の気持ちもわからないでもない。から。
田中屋のシティスナップ「湘南の女」


湘南スナップ 撮影/田中宏明
連載小説「女も三年目から」作/奈良あひる
六月の朝、真紀はカーテンを開けた。
雨上がりの光が、まだ濡れたベランダの鉢植えに反射している。
小さな紫陽花の花が、ゆっくりと首を上げていた。
その様子を見て、真紀は思った。
――花も人も、陽にあたることを忘れないのだと。
部屋の中では、トーストの香りが漂っていた。
最近は、珈琲を淹れるとき、あの夜のことを思い出すことも少なくなった。
浩一とは、それきり会っていない。
でも、不思議と寂しくはなかった。
別れのあとにも、静かな感謝が残ることを、真紀は初めて知った。
ポストから取り出した郵便の中に、一通のハガキがあった。
職場の同僚、村井からだった。
淡い水色のインクで、短い言葉が並んでいる。
「来週の土曜、あのカフェでランチでもどうですか。
ずっと話したいことがあるんです。」
真紀は、ハガキを手にしたまま立ち尽くした。
胸の奥が、わずかにざわめいた。
“話したいこと”――その曖昧な響きが、朝の光に溶けていく。
洗面所の鏡の前に立ち、自分の顔を見つめた。
少し髪が伸びて、頬の線が柔らかくなっている。
女は、悲しみを経るたびに顔つきが変わる。
その変化を、受け入れる準備がようやく整った気がした。
トーストを半分残し、真紀は出かける支度を始めた。
外は風がやさしく、空の色が淡い。
歩くたび、靴の底がアスファルトを軽く叩く音がした。
それが、まるで心臓の音のように感じられた。
ふと、信号待ちの間に携帯が震えた。
画面には「浩一」の名前。
真紀は、ほんの一瞬だけ指を止めたが、結局開かなかった。
きっと、季節のあいさつか何かだろう。
それで十分だった。
カフェの前に着くと、村井がすでに待っていた。
グレーのシャツに薄い笑み。
その表情に、どこか穏やかな誠実さがあった。
「久しぶりですね」
「ええ、ほんとに」
ふたりは窓際の席に座った。
外では街路樹の葉が風に揺れている。
その光が、真紀の指先に反射して小さくきらめいた。
村井は、言葉を探すように口を開いた。
「この前、あなたがひとりで残業してるのを見て……
なんだか、声をかけたくなって」
真紀は、微笑んだ。
その笑みは、守るためではなく、ようやく“開く”ためのものだった。
珈琲が運ばれてくる。
湯気の向こうに、かつての夜の記憶が一瞬だけよぎった。
けれど、もう痛くはなかった。
ただ、人生のひとつの景色として、静かに遠ざかっていく。
真紀は思った。
――人は誰かに裏切られても、また誰かに出会う。
それが、生きるということなのかもしれない。
店を出ると、雨上がりの風が頬を撫でた。
空は、薄い青。
真紀の心にも、同じ色が映っていた。

おしまい



