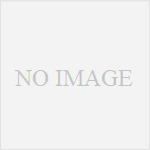「カメラの奥の微熱(官能+耽美表現強化版)」
秋のはじまりの気配が、夜の街をゆっくりと冷やしていた。
その夜、彼女から一本の電話がかかってきた。まるで夢の続きのように。
「今日、撮っていたの。あなたのことを――無意識に」
その声の湿り気に、私は体温が少し上がるのを感じた。
彼女の言葉はいつも、現実の輪郭をわずかに歪める。
乾いた都会の夜に差し込む、白い息のような存在だった。
旧い洋館跡地の公園。石畳の道に、朽ちかけた灯が落ちる。
影と光が交わるたび、私たちの距離も、すこしずつ縮んでいった。
彼女は言った。「光って、誰かの秘密を優しく包むものだと思うの」
撮影は、儀式のように静かだった。
彼女はレンズ越しに私を見つめながら、少しずつ、手を伸ばしてくる。
指が頬をなぞり、髪に触れ、首筋に置かれた瞬間――
私はもう、この夜が帰れないものになると知っていた。
撮影が終わるころ、彼女の目はどこか熱を帯びていた。
黙ったまま手を取られ、彼女の部屋へと導かれる。
抵抗はしなかった。むしろそれを、ずっと待っていたような気さえした。
小さな灯りひとつだけの部屋。
カメラが静かに置かれたその横で、彼女は私の服に手をかけた。
一枚ずつ剥がされる布は、皮膚より先に、心の殻を脱がせていく。
「あなたの呼吸、見ていると落ち着く」
彼女がそう呟きながら、胸元に唇を落としたとき、
全身が、じわじわと熱を帯びていった。
ベッドの上、何も語らずに、互いの肌が言葉を交わす。
指先が探り、脚が絡まり、吐息がかすれ、
声にならない音が、何度も部屋に満ちた。
彼女の動きは柔らかく、時に鋭く、
どこか痛みと悦びの境界を踏み越えるようで、
その一瞬一瞬が私の奥の、何か深い場所を照らしていた。
終わったあと、私はしばらく天井を見つめていた。
肌にはまだ、彼女の手の温もりが残っていた。
太ももの内側には、微かな疼きと、確かな痕跡。
シーツの中で重なった身体のぬくもりが、
ただの肉体のものではなかったことを、
私の奥の奥が知っていた。
彼女は何も言わず、私の指に触れ、
まるで写真のピントを合わせるように、目を細めた。
「あなたの輪郭、ちゃんと焼きついた」
朝、目覚めると彼女の姿はなかった。
窓辺に、彼女の走り書きが一枚。
「次は、私を撮って」
私はカーテンを開け、光に手をかざした。
まだ身体の奥に残る余韻は、決して夢のなかのものではなかった。
あの夜、私は確かにひとつの物語の中に触れられ、
そして今も、その中にいる。