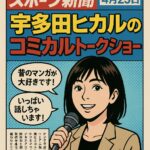ラッツ&スターと田代まさし
ラッツ&スターにおいて、田代まさしの存在は一種の「媒介」だった。グループを象徴するサングラスに黒塗り姿、その中で彼は決してメインボーカルではなかった。しかし、リードシンガーである鈴木雅之の重厚な声と、桑野信義の華やかなトランペットやコーラスが響きわたるなか、田代はユーモアと軽妙さをまとって全体をつなぎ、観客の耳と目をリラックスさせる役割を担っていた。言い換えれば、彼は「間」を司る人間だったのだ。
ラッツ&スターの音楽は、ドゥーワップを基盤にした正統派のハーモニーでありながら、演出においてはどこか洒脱で遊び心に満ちていた。そこに田代が立つことで、音楽の真剣さとバラエティ的要素との均衡がとれていた。彼は振付けや身振りで曲の雰囲気を補強し、ときには軽いギャグを交えながら空気を和ませた。これは単なる添え物ではなく、むしろ彼がいるからこそ「大人の遊び」としてのラッツ&スターが完成していた、といっていい。
また、田代の声はコーラスに溶けることで、前面に出過ぎることなく独特の厚みを加えていた。音楽的な才能だけを見れば、突出したリードを取るメンバーではない。だが、グループにおいて「主役を支える」ことこそが彼の芸風と響き合い、聴衆の記憶に残る色彩を添えていたのである。
さらに、テレビ番組やメディア出演において田代は橋渡し役を果たした。硬派で本格的な音楽集団というだけでなく、親しみやすさを備えたグループとして世に広がる過程で、彼のユーモアと身近さが大きな役割を果たしていたのは疑いない。つまり田代は、音楽と大衆とのあいだに立ち、その距離を自然に縮める媒介者だった。
ラッツ&スターはその名の通り「スター」でありながら、同時に「ラッツ」、つまり街角の匂いを持つ存在であった。その両面を象徴するのが、田代まさしという人物だったのだ。音楽の品格を崩すことなく、しかし近寄りがたい敷居をも作らない。その微妙なバランスを保つ役割を、彼は自然体で演じていた。
グループを振り返るとき、田代の立ち位置は決して目立つものではない。しかし彼がいたからこそ、ラッツ&スターは単なるドゥーワップ・グループにとどまらず、日本の大衆文化の中で「音楽と笑いとスタイルの融合」という稀有な存在になりえたのだ。
体調不良商法
世界の終わり、サカナクション
田中屋のシティスナップ

連続小説「女の風景写真」第37話 作/奈良あひる
部屋の明かりは少し落とされていた。
わずかな灯りの中で、三人の影がゆっくりと揺れる。
言葉はもう必要なかった。呼吸の強さや、指先のわずかな動きが、すべてを伝えていた。
由紀子の心臓の鼓動が、耳の奥で波のように広がっていく。
夫の呼吸、男の体温――それぞれが違うリズムを持ちながら、少しずつひとつに融けていった。
誰の手がどこにあるのか、もう分からない。
それでも、不思議と怖くはなかった。
この瞬間だけは、世界の境目がやわらかくほどけていく気がした。
夫の声が、低く、息に混じって響く。
「……由紀子」
名前を呼ばれただけで、胸の奥が熱くなる。
続いて、反対側から短い息づかいが重なった。
それは合図のようでもあり、承認のようでもあった。
由紀子は、二人の間で揺れる感情をまるごと抱きしめた。
愛情、罪悪感、幸福、そして快い痛みのようなもの――
それらすべてが一斉に溶け合い、言葉にならない震えを生み出していた。
どれほど時間が経ったのか分からない。
気がつけば、部屋の空気は少しひんやりとしていた。
窓の外の夜気が、静かに流れ込んでくる。
三人は肩を寄せ合いながら、しばらくのあいだ動かなかった。
言葉を交わさなくても、互いの鼓動がまだ続いているのを感じ取っていた。
由紀子はゆっくりと目を閉じた。
――ここまで来てしまった。
でも、後悔ではない。
むしろ、何かを生きてしまったという実感が、身体の奥から確かに湧き上がっていた。
つづく